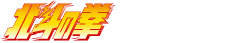でもね。そうやっていく内に、ケンシロウってどんどん言葉が少なくなっていくんだよな。背負っていくものが多いから、高倉健みたいになっちゃう。無言でも闘うみたいなね。それがケンシロウの成長なんだけどね。
──でも、そのユリアが南斗最後の将だったというのは、ある意味では究極のサプライズでした。じつはユリアが生きていた(※4)。

【※4】生きていたユリア
ユリアの生存は、サザンクロスから身を投じた際、地上に落ちた描写が行われていなかったこともあり「五車星に守られた」という設定が加えられた。その回想シーンでは久しぶりにシンが登場。ユリア殺しの悪名をかぶりケンシロウと決着をつけるという、彼なりの美学も描かれた。ケンシロウとシンの闘いに“深み”が増したのだ。
これ…(しばらく考え)…賭けだったよね~。あまりにも唐突じゃないかっていうのがあって。でも、そこに賭けないと話が転がらないから。
──転がらないと言いますと?
本来は使い道が無いのよ。ただの弱い女で。ユリアが生きていたことにしようかという話が出て、それをどうにかしないといけないとなって。
──当時は「マジかよ~」とか言いながら読んでたんですけど、結局、ケンシロウとラオウの最後の闘いに進むまでの重要な人物になって、気づいたら文句を言わなくなってて。
南斗最後の将にすると、死なずに済んだことの理由付けもできるし、空白の時間は身を隠していたということで収まる。結局、その賭けによって五車星という味方が生まれて、ラオウの足止め役になったりした。
──ケンシロウとユリアを引き合わせようとする流れ…大義名分みたいなものができましたよね。
うん。俺も最初はどうかなと思ったんだけど、ユリアが生きていたお陰でケンシロウとラオウの闘いまでの話を膨らませられたし、ラオウが哀しみを背負う描写も書けた。
──哀しみを背負うという、子供には無い感覚が、闘いをより壮大なものにしてくれた感はあります。
結局「ケンシロウってなんで生きてるか?」っていうね。まず、子供のころにシュウに助けられ、今度は核戦争でトキに救われた。コイツは背負っていくものがあって、生かされて強くなっていくという。つまり、生きなきゃいけないんだよ。
──う~ん。生かされているから、生きなければならない。深いですね。
ケンシロウのために何人が死んでくれたかってことでね。ケンシロウは生かされてきたから死ぬわけにはいかない。でもラオウは逆で、ぜんぶ殺して生きてきた。無敗であるがゆえに、なんにも無いんだよ。
──あ~~~。なるほど。ラオウには圧倒的な強さがあるんだけど、無敗であるがゆえの弱さ、もろさ。そういうものも持ち合わせている。
つまり、ラオウの欠点は1回も負けてないってことなんだよね。だからフドウを前にした時に「あれ?」ってなるわけじゃん。あそこでラオウはキャラクターが変わるんだよ。
──恐怖が蘇ることになるフドウとの闘いですね。あれは精神的な敗北というか、自分を射なかった拳王軍に対するあの激昂ぶりは、もしかすると敗北を知らないがゆえの戸惑いが、怒りとして表れたのかもしれませんね。ある種の、焦りが。
そう。自分に足りないものがあると気づくわけだ。
──この時は、話がすごく深いところまで行ってるなと思うんです。生き死にが哲学的になってきて。
乗ってる時期なんだよね、俺自身。だから漢の強さ、格好良さの出し方。そういうものが、いちばん俺の中で出てた時なんだろうね。年齢で言うと37才とか38才くらいの時期。
──それ、いまの俺です。ほぼその年齢なんで。乗ってるどころか、乗ってた先生の書いた物語を、延々と30年ほど読んで、乗ってます。
ははは。でも、結局はどうやって泣かせるかっていうところもあってね。
──ものの見事に、ほとんどのシーンで泣いてました。
泣かせたら残酷なシーンが全部、消えてくれるんで。
──あ~。そうですね、たしかにそうですね。サウザーの最期で泣いたからこそ、あの残虐な生き方をも認めてしまったという(※5)。

【※】サウザーの最期
トキが得意とする有情拳でケンシロウに敗れたサウザーは、最期にそれまでの残虐性が嘘であったかと思えるほどの穏やかな表情を見せた。非情の道を選ばざるを得なかった哀しい漢の最期はファンの涙を誘い、結果として、この「サウザー編」は多くのファンにベストバウトと評され、いまなお色あせず語り継がれる物語となった。